戦国時代、日本には「キリシタン大名」と呼ばれるキリスト教を信仰した武将たちがいました。
特に 大友宗麟(おおとも そうりん)、高山右近(たかやま うこん)、小西行長(こにし ゆきなが) の三人は、キリシタン大名として広く知られています。
彼らは宣教師を庇護し、領内にキリスト教を広めるとともに、貿易を通じて西洋の文化や技術を積極的に取り入れました。
彼らがどのようにしてキリスト教に惹かれ、どんな影響を与えたのかを詳しく見ていきましょう。
 ルイ氏
ルイ氏全国でも有名な3人かな
大友宗麟-九州最大のキリシタン大名
大友宗麟 は、九州の豊後国(現在の大分県)を治めた大名です。
キリスト教を積極的に受け入れたことで有名。
彼はポルトガルとの交易を重視し、領内に教会を建てるなど布教活動を支援しました。
キリシタン大名になったきっかけ
1578年にキリスト教の洗礼を受け、「フランシスコ」の洗礼名を得ました。
彼はポルトガルとの貿易を重視し、南蛮文化を積極的に受け入れたことがキリスト教受容の大きな要因です。
大友宗麟の生涯
- キリスト教の庇護
- ポルトガルとの貿易促進
- 日向侵攻と挫折
キリスト教の庇護
領内に教会やセミナリオ(神学校)を建設し、多くの家臣や領民をキリシタンに改宗させた。
ポルトガルとの貿易促進
南蛮貿易を通じて、鉄砲や海外の技術を積極的に導入。
日向侵攻と挫折
1578年、キリスト教徒を支援するため日向(現在の宮崎県)に侵攻。
しかし耳川の戦いで島津軍に大敗し、その後勢力を失っていく。
高山右近-信仰を貫いた不屈のキリシタン武将
高山右近 は、摂津(現在の大阪府・兵庫県)を拠点とした武将です。
幼少期からキリスト教に親しみ、生涯にわたって信仰。
徳川幕府のキリスト教弾圧にも屈せず、1614年にマニラへ追放され、現地で亡くなりました。
キリシタン大名になったきっかけ
高山右近の父は、摂津を治めた戦国武将の高山飛騨守です。
父がキリスト教に改宗した影響で、右近も少年期からキリスト教と深く関わるようになりました。
彼は熱心なキリシタンとして知られ、領内に多くの教会を建てます。
高山右近の生涯
- キリスト教の布教活動
- キリスト教弾圧への対応。
- マニラへの追放と死
キリスト教の布教活動
領地でのキリスト教信仰を奨励し、多くの民衆を改宗させた。
キリスト教弾圧への対応
豊臣秀吉の「バテレン追放令」後も信仰を捨てることなく、徳川幕府の「キリスト教禁止令」により領地を没収された。
マニラへの追放と死
1614年、徳川家康の命令により、多くのキリシタンと共にマニラへ追放された。
現地では信仰の篤さを称えられ、現在も「聖人」として敬われている。
小西行長-宣教師を支援した戦国武将
小西行長 は、堺の豪商の家に生まれ、豊臣秀吉に仕えて大名となりました。
キリスト教に深く帰依し、領内に教会を建てるなど布教を支援します。
関ヶ原の戦いで敗北後、キリスト教徒であることを理由に改宗を迫られたが拒否し、処刑されました。
キリシタン大名になったきっかけ
小西行長は、もともと堺の豪商の家に生まれましたが、豊臣秀吉に仕えて大名となりました。
1583年に洗礼を受け、熱心なキリシタンとして活動しました。
小西行長の生涯
- キリスト教布教の支援
- 朝鮮出兵での活躍
- 関ヶ原の戦いでの悲劇
キリスト教布教の支援
領内に教会を建て、宣教師の活動を支援。
朝鮮出兵での活躍
豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)で日本軍の先鋒を務める。
関ヶ原の戦いでの悲劇
関ヶ原の戦いで西軍に属し敗北。
敗戦後、キリスト教徒であることを理由に改宗を迫られたが拒否し、最終的に処刑された。
まとめ
大友宗麟、高山右近、小西行長の3人は、それぞれ異なる背景を持ちながらも、キリスト教を受け入れ、その信仰を貫いたキリシタン大名でした。
彼らの生き方は、日本におけるキリスト教の歴史に今も深い影響を与えています。
彼らの足跡をたどり、戦国時代のキリシタンの歴史に思いを馳せてみるのも興味深いかもしれません。
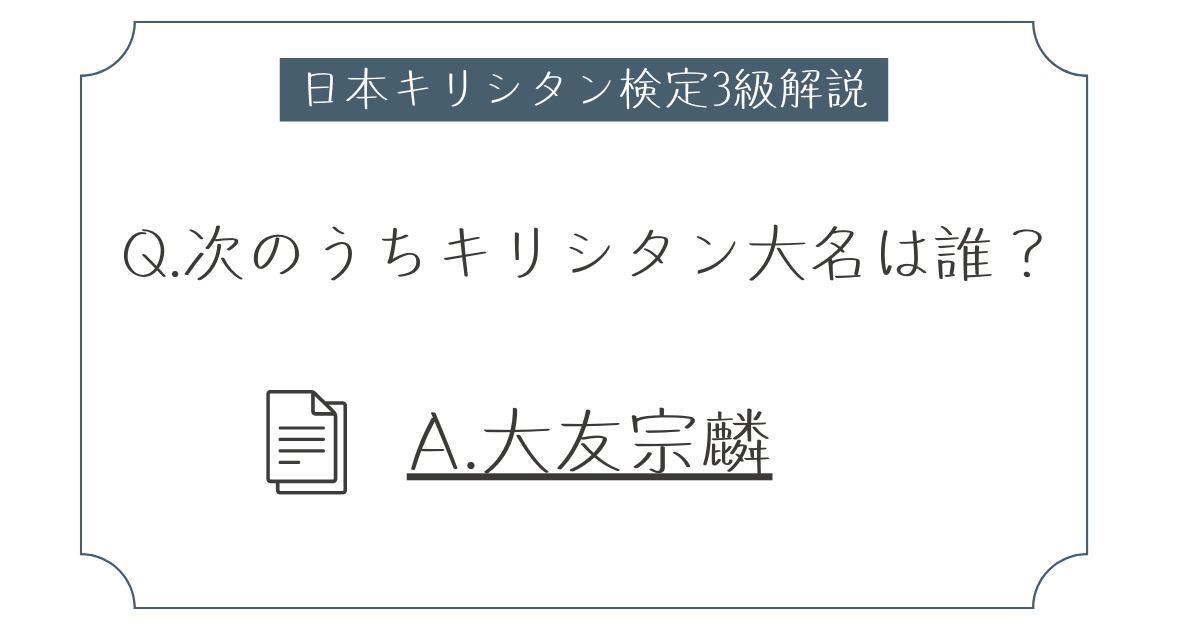
コメント