江戸幕府の時代、日本ではキリスト教が厳しく弾圧されていました。
明治時代に入ると、徐々に宗教に対する姿勢を変えていきます。
そして1873年、ようやくキリスト教禁教政策が撤廃されました。
本記事では、1873年に禁教が解かれるまでの経緯や背景について詳しく解説します
江戸時代の禁教政策
江戸幕府は1600年代初頭からキリスト教を危険視し、厳しい弾圧を行いました。
キリスト教が幕府の統治を脅かし、外国勢力との結びつきを強める可能性があると考えられたためです。
- 1612年: 幕府が直轄領でキリスト教の布教を禁止。
- 1613年: 江戸幕府がキリスト教徒を処罰する方針を明確化。
- 1614年: 全国的にキリスト教の禁教令を発令。
- 1620~1630年代: 江戸幕府が本格的なキリスト教弾圧を開始。
- 1637~1638年: 島原の乱が発生。
- 「踏み絵」や密告制度: 密告制度により多くのキリシタンが捕えられた。
このように、江戸時代を通してキリスト教は「邪宗」として扱われ、信者たちは過酷な状況に置かれていました。
明治時代初期の宗教政策
明治政府が誕生すると、近代化と国際関係の強化が求められるように。
しかし、当初は江戸幕府の禁教政策をそのまま引き継ぎます。
- 1868年:「五榜の掲示」によりキリスト教禁止再確認される。
- 1869年:長崎で信徒約3,400人が逮捕・流罪に処される。
- 1871年:外国との交渉の中で、キリスト教弾圧の批判が強まる。
- 欧米諸国の圧力: 欧米各国は条約改正の条件として、宗教の自由を求める。
このように、明治政府は国内では禁教政策を継続
しかし、国際社会からの圧力を受け、宗教政策の転換を迫られていました。
1873年の禁教撤廃とその影響
日本政府は、外交問題の解決や近代国家の構築を進めるため、キリスト教に対する方針を転換。
1873年(明治6年)、日本政府はキリスト教禁教令を正式に撤廃します。
影響①:カトリック教会の復活
禁教が解かれると、多くの隠れキリシタンがカトリック教会に戻り、正式に信仰を続けるようになった。
影響②:プロテスタントの伝来
欧米のプロテスタント宣教師も活発に布教を開始し、日本各地にキリスト教学校や病院を設立。
影響③:宗教の自由への道:
その後、日本では信教の自由が徐々に認められます
- 1889年:「法律の範囲内で信教の自由」が保証される。
- 1899年:外国人宣教師の活動が正式に認められる。
ただし、国家神道の影響もあり、キリスト教を含む他宗教は一定の制約を受け続けました。
このように、1873年の禁教撤廃は、日本の宗教政策の大きな転換点となったのです。
まとめ
- 江戸幕府は1612年からキリスト教を禁じた
- 明治時代になってもキリスト教は依然として禁止
- 日本政府は1873年にキリスト教の禁教政策を撤廃
- 禁教撤廃後、布教を本格化しキリスト教が再び広がった。
- 1889年に信教の自由が認められた。
- 1899年には外国人宣教師の活動が正式に認められた。
明治政府は、国際社会の要求や近代化の流れの中で、宗教政策の改革を余儀なくされました。
1873年のキリスト教禁教撤廃は、日本における信教の自由への第一歩となり、その後の宗教政策に大きな影響を与えたのです。
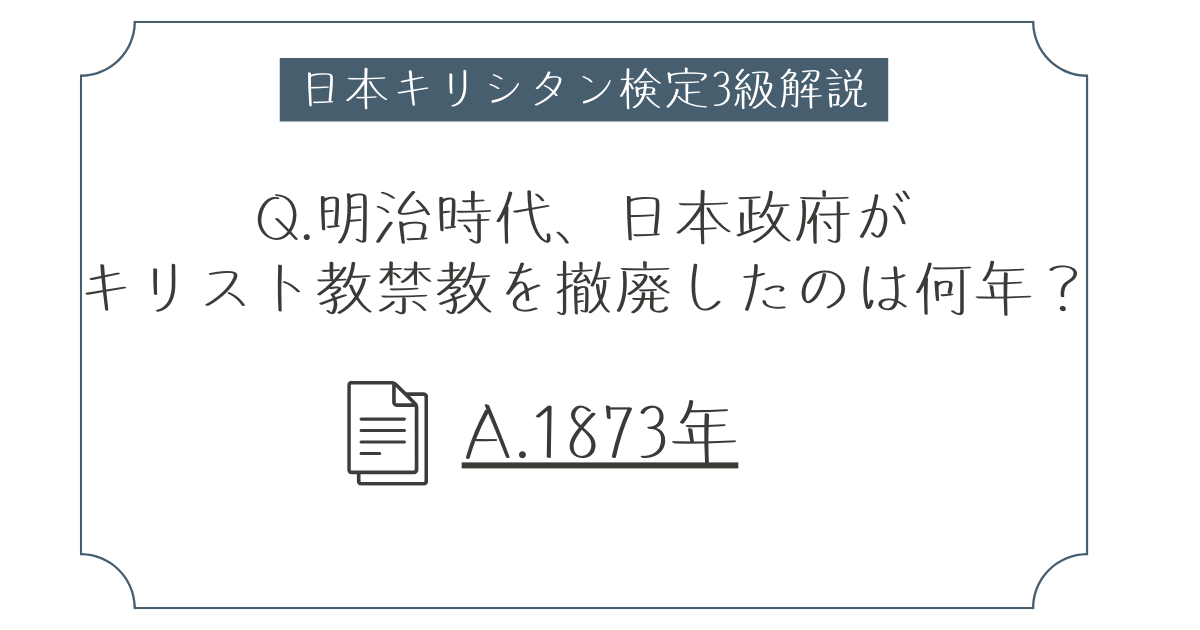
コメント