キリスト教布教により日本で
流通した外国の品物を何と呼ぶ?
戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本にはヨーロッパから様々な品物や文化が流入します。
16世紀半ばにポルトガル人やスペイン人が来航し、キリスト教の布教とともに「南蛮貿易」が盛んに行われるようになりました。
この貿易によってもたらされた品物は「南蛮貿易品」として珍重されます。
南蛮貿易品は、日本の生活や文化にも大きな影響を与えました。
本記事では、南蛮貿易によってもたらされた品物と、それが日本に与えた影響について詳しく見ていきます。
南蛮貿易の始まりとキリスト教の布教
16世紀中頃、日本に初めてヨーロッパ人が来航しました。
1543年、ポルトガル人が種子島に漂着し、中国商人を通じて鉄砲を日本にもたらしたことを皮切りに、南蛮貿易が始まります。
その後、フランシスコ・ザビエルが日本に来訪し、キリスト教の布教が本格的に始まりました。
キリスト教の布教とともに、ヨーロッパの品物や文化が日本に流入します。
ポルトガル人やスペイン人は日本の商人や戦国大名と積極的に貿易を行い、武器や工芸品、食べ物など様々な品が日本に持ち込まれました。
日本にもたらされた南蛮貿易品の例
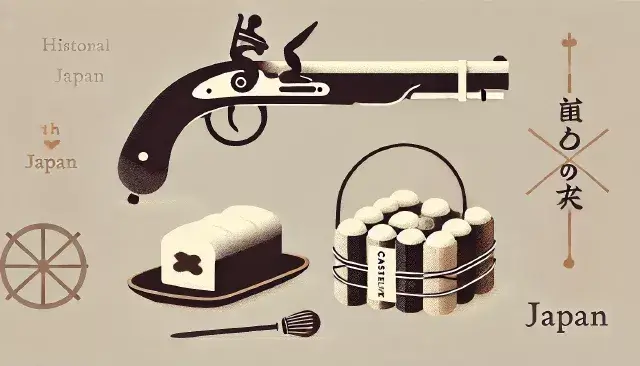
南蛮貿易を通じて、日本にはこれまでになかった新しい品物や技術、文化がもたらされました。
戦国大名たちは、武力を強化するための武器や軍事技術を求めます。
商人たちは、貴重な輸入品を取引することで富を築きました。
食文化や工芸品の分野でも、南蛮貿易が日本に与えた影響は大きく、後の時代にもその名残が見られます。
鉄砲(てっぽう)
日本の戦国時代における戦術を大きく変化させた武器。
特に織田信長は鉄砲隊を編成し、戦術的に活用した。
② カステラ
ポルトガルから伝わった南蛮菓子の一つ。
長崎を中心に広まり、現在でも人気のあるお菓子として親しまれている。
③ ラシャ(羅紗)
ヨーロッパからもたらされた高級な毛織物で、日本の武士や上流階級の間で珍重された。
南蛮貿易を通じて輸入され、衣服や装飾品に使用された。
南蛮貿易品と日本社会への影響

南蛮貿易によってもたらされた品々は、日本の文化に大きな変化をもたらしました。
貿易による物品の流入だけでなく、日本人の芸術や文化にも影響を与えます。

その代表例が「南蛮屏風(なんばんびょうぶ)」
南蛮屏風は、16世紀末から17世紀初頭にかけて日本で制作された屏風絵。
ポルトガル船や南蛮人(ポルトガル人・スペイン人)の姿が描かれています。
これらの屏風は、南蛮貿易によってもたらされた異国文化への憧れを反映しており、当時の日本人が南蛮人や彼らの文化をどのように見ていたのかを知る貴重な資料となっています。
まとめ
南蛮貿易とは?
→ 16世紀半ばから江戸時代初期にかけて行われた、ポルトガル人やスペイン人を中心とする貿易。
日本とヨーロッパの直接貿易だけでなく、東南アジア経由の交易も含まれる。
南蛮貿易で輸入された代表的な品物
① 鉄砲(戦国時代の戦術を変えた武器)
② カステラ(ポルトガル由来の南蛮菓子)
③ ラシャ(毛織物)(ヨーロッパから輸入された高級織物)
南蛮貿易がもたらした影響
→ 戦国時代の戦術の変化(鉄砲の普及)
→ 食文化の発展(カステラや南蛮料理の広まり)
→ 異国文化への憧れ(西洋風の服飾・家具・工芸品の流行)
→ 美術への影響(南蛮屏風の制作)
南蛮貿易は、戦国時代の日本に新しい技術や文化をもたらします。
当時の日本人にとっては、異国の文化との出会いでした。
また、南蛮貿易を通じて生まれた異国文化への関心は、日本美術にも影響を与えます。
江戸時代に入るとキリスト教が禁止され、南蛮貿易も制限されましたが、その影響は日本文化の中に深く刻まれました。
南蛮貿易がもたらした文化や技術は、やがて日本独自の形に発展し、現代にもその名残を残しています。
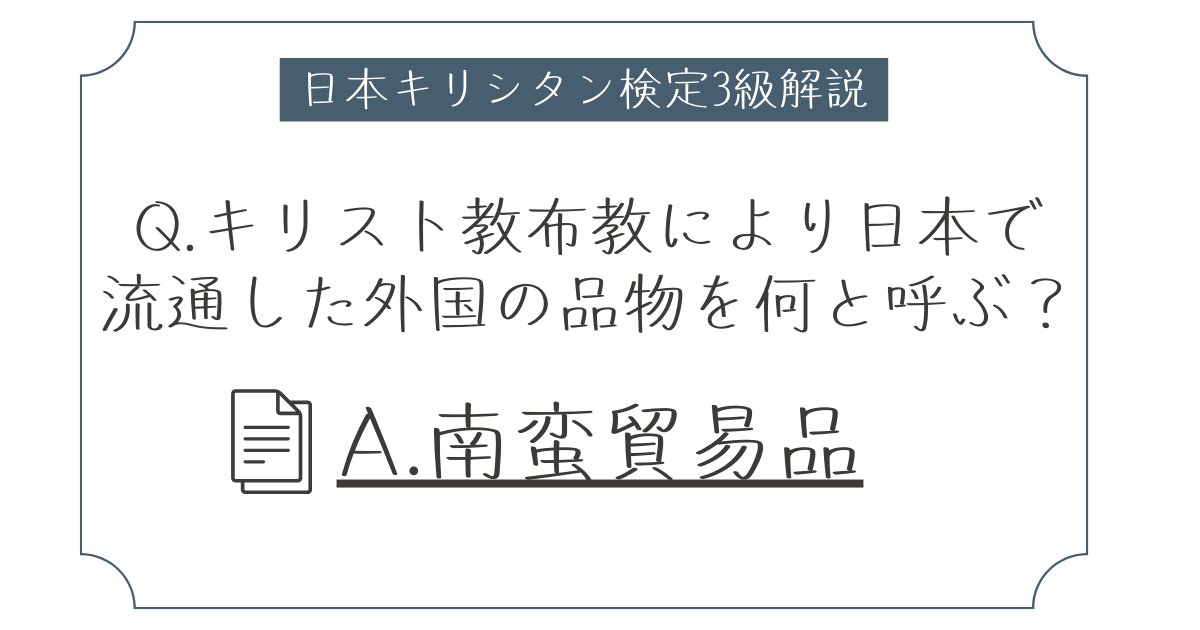
コメント