江戸時代、幕府はキリスト教を「危険な宗教」として厳しく弾圧しました。
しかし、その弾圧に耐えかねたキリシタンたちが起こした大規模な反乱があります。
それが 「島原の乱」 です。
本記事では、日本キリシタン検定の問題を通じて、島原の乱がどのようにして起こり、どのような結末を迎えたのか を分かりやすく解説します。
島原の乱が起こった背景
江戸幕府ではキリスト教が厳しい監視下に置かれ、最終的に禁教となりました。
1614年には「禁教令」が発布され、キリシタンに対する弾圧が始まります。
九州地方ではキリシタンの信者が多く、領主による過酷な年貢の取り立てが続いていました。
これにより、農民たちは極端な貧困に追い込まれていきます。
1637年、以下の問題が重なり、島原・天草の農民たちは一揆を起こしました。
島原・天草の住民の不満
重税による生活苦
島原藩主・松倉勝家(かついえ)と唐津藩主・寺沢堅高(かたたか)は、財政難を解決するため、農民に過酷な年貢を課した。
キリシタン弾圧
キリシタン信者に対して厳しい弾圧が行われ、処刑される者も多かった。
天候不順による飢饉
1630年代後半、干ばつや冷害により農作物が不作となり、さらに苦しい状況に。
島原の乱と天草四郎
島原の乱の指導者となったのが、天草四郎(あまくさ しろう) です。
天草四郎とは?
本名は 益田時貞(ますだ ときさだ)。
キリシタンの家に生まれたとされ、信仰心が厚い人物でした。
天草四郎は神の子として奇跡を起こすという噂が広まり、人々の信仰の対象となります。
島原・天草の農民やキリシタンたちは、「天草四郎が導いてくれる」と信じ、彼のもとに集まりました。
一揆の展開
島原・天草の反乱軍は、島原の原城を拠点とし、幕府軍との攻防をくり広げます。
最初は地の利を活かして善戦し、幕府軍を何度も撃退しました。
しかし、幕府側は兵力を増強し、最終的には約12万の大軍で原城を包囲します。
約3か月間の籠城戦の末、1638年2月、幕府軍が総攻撃を開始し、原城は陥落。
天草四郎を含む反乱軍約3万7千人は殺され、生き残った者もほとんどいませんでした。
島原の乱の影響
島原の乱は、幕府にとって大きな衝撃となりました。
3万7千人もの農民やキリシタンが命を落とした戦いは、日本史上最大規模の一揆。
島原の乱をきっかけに幕府はキリシタン弾圧をさらに強化し、日本の鎖国政策を確立します。
幕府の対応
キリスト教への弾圧がさらに強化
島原の乱をきっかけに、幕府はキリシタンを危険視し、より厳しく取り締まるようになった。
鎖国政策の確立
1639年、幕府はポルトガル船の来航を禁止し、外国との交易を大幅に制限する鎖国政策を確立した。
幕府の農政見直し
幕府は、農民が再び大規模な一揆を起こさないよう、農政の見直しを行ったとされる。
原城跡と現在
島原の乱の舞台となった原城跡は、史跡として保存されています。
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一部として登録。
島原の乱の歴史は、今もなお語り継がれています。
まとめ
- 1637年、キリシタンと農民が幕府に対して反乱
- 島原の乱の主な原因は、重税・飢饉・キリシタン弾圧の3つ
- 天草四郎は反乱軍の象徴的人物
- 反乱軍は原城に籠城、幕府の大軍により1638年に壊滅。
- 島原の乱をきっかけに、幕府は鎖国政策の確立を進めた。
島原の乱は、日本史上最大級の農民一揆であり、キリシタン弾圧の象徴的な出来事でした。
この乱により幕府はキリスト教の禁止をさらに徹底し、日本はより閉鎖的な鎖国の時代へと突き進みます。
現代でも、長崎県の原城跡を訪れることで、当時のキリシタンたちの信仰と苦しみを感じ取れます。
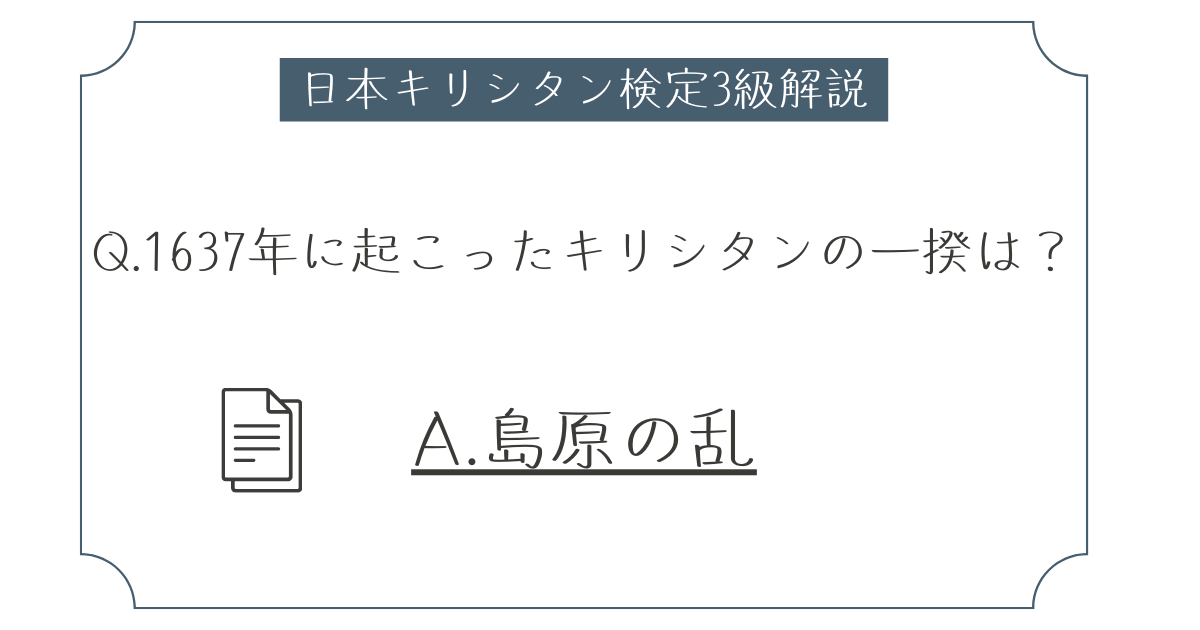
コメント